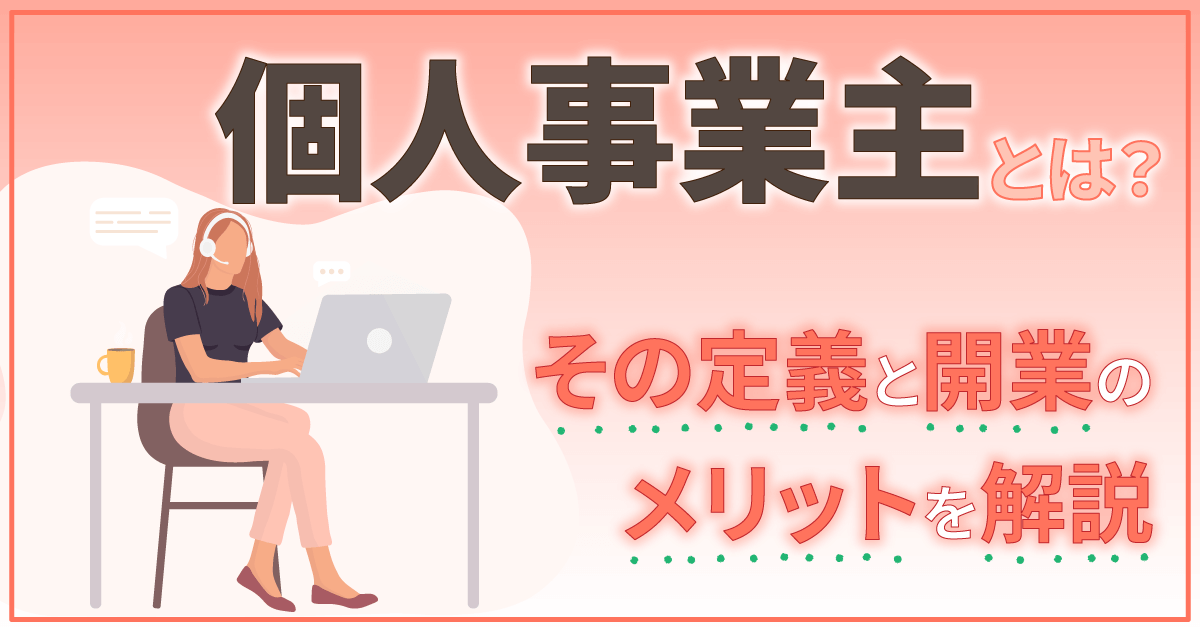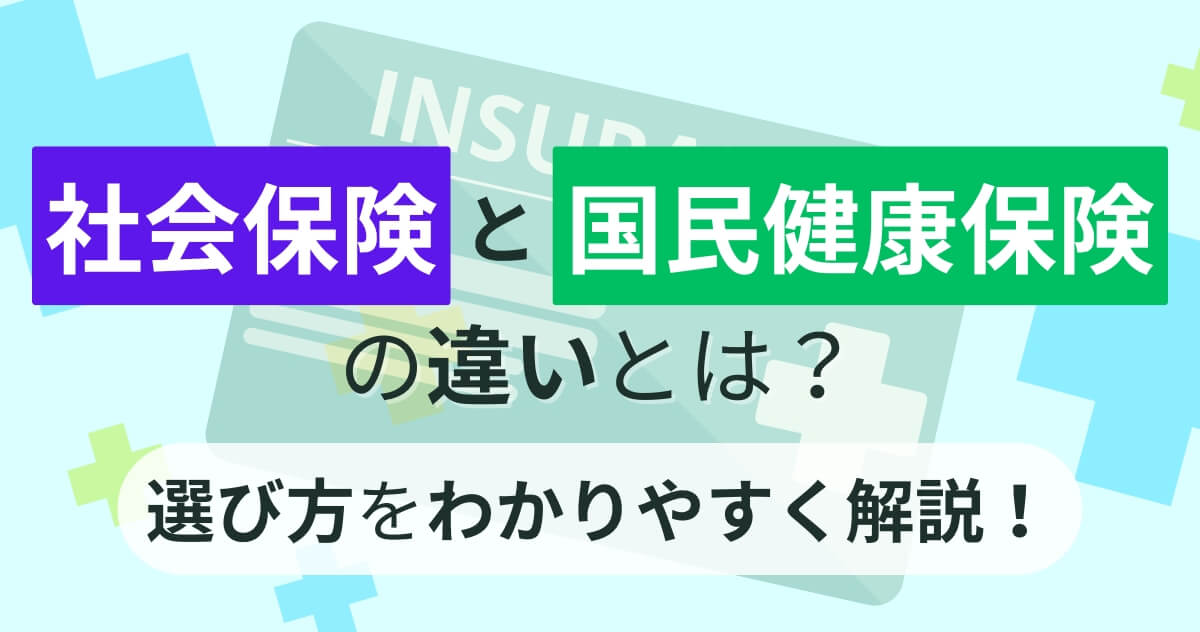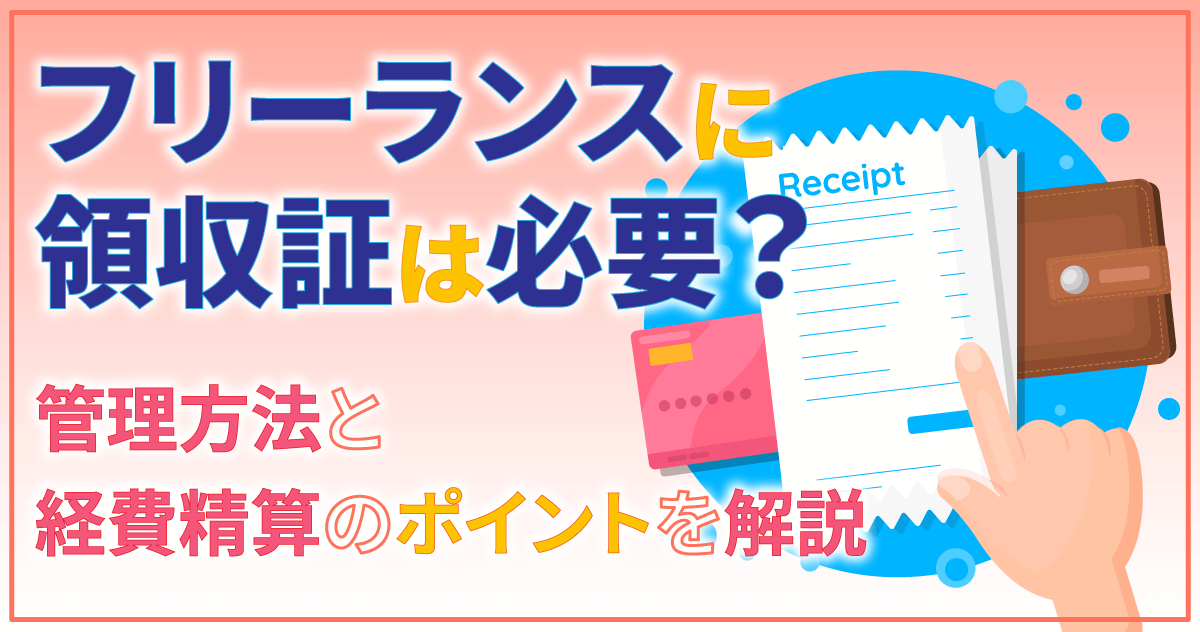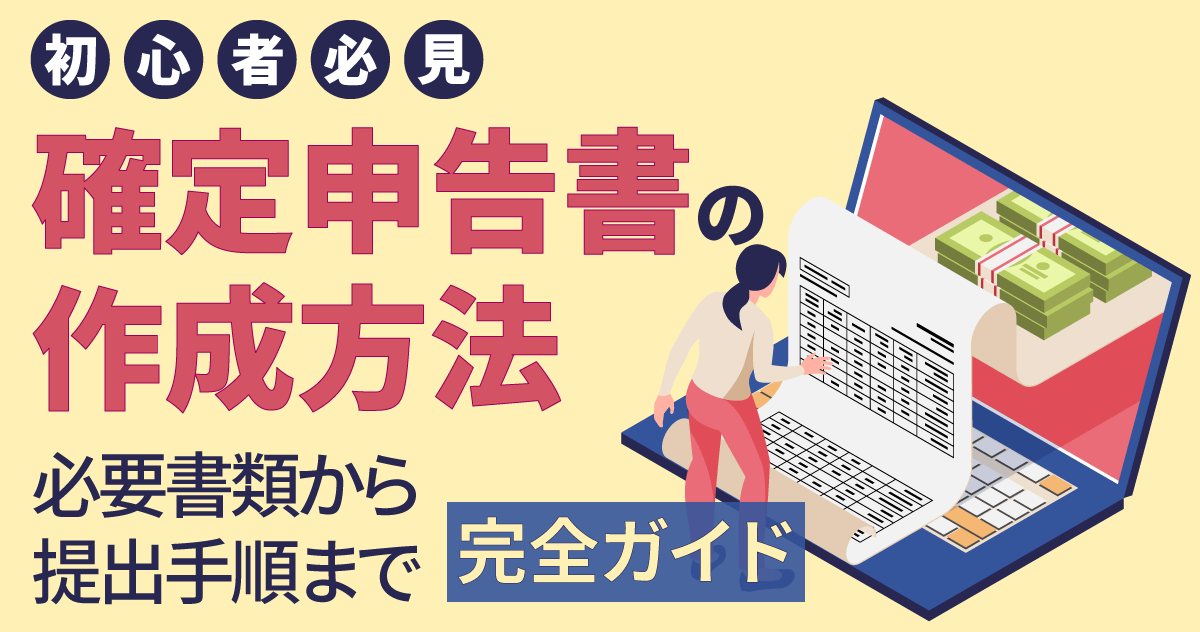フリーランスが扶養内で働くには?条件や手続き方法を解説

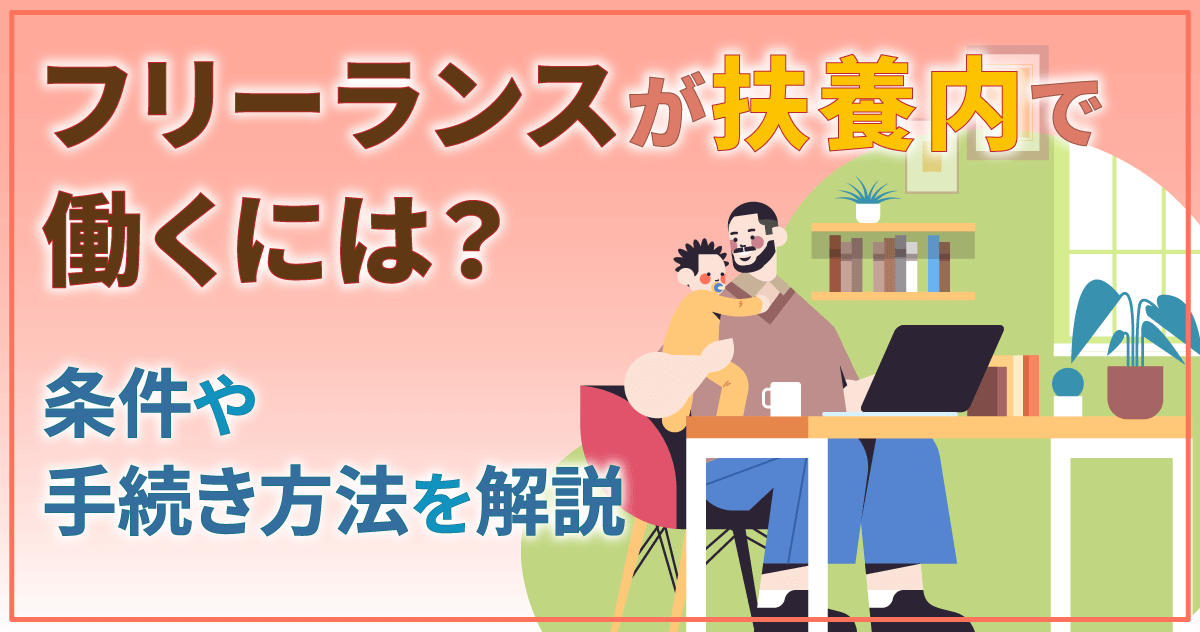
はじめに
- 扶養に入ることで健康保険料や年金保険料の負担がかからないメリットがある
- 扶養には社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類がある
- 社会保険における扶養の条件は年収130万円未満が原則である
- 税法上の扶養控除を受けるには合計所得金額が48万円以下でなければならない
- 扶養条件を維持するには年間収入を常に意識するようこころがける
フリーランスを始める際に、扶養内で働けるのか気になったことはありませんか? 近年、働き方改革の時代により、フリーランスとして働く人が増えました。中には配偶者の扶養内で働く人も少なくありません。しかし、年収の壁に対して、フリーランスが働く上でどのような基準や条件で見ればいいのか、不安や疑問を抱えたことはあると思います。本記事で扶養に入るための手続き方法と流れを理解し、年収基準や所得を超えないためのコツとともにポイントを見ていきましょう。
フリーランスが扶養内で働くとは?
そもそも扶養内で働くとは、生計を立てていくのが難しい場合に、配偶者や親など身内からの経済的な援助を受けながら働くことです。扶養に入ることで社会保険料や税金などの負担を経済的に減らすといった目的があります。
扶養内で働くメリット・デメリット
扶養に入る上でのメリットやデメリットとは一体どのようなことなのでしょうか? 以下、それぞれについて説明します。
メリット
健康保険料や年金保険料を自分で負担しなくとも良いというメリットがあります。たとえば国民健康保険に加入した場合、毎月数万円の支払いを必要とします。しかし、配偶者の扶養に入れば、国民健康保険や国民年金に加入する必要がなくなり、毎月の保険料負担が大幅に軽減されます。仕事と収入が不安定なフリーランスにとって、税金や社会保険料を節約できるという点では大きなメリットでしょう。
デメリット
逆に、扶養に入ることで年収に制限がかかるため「もっと働きたい」と思っていても、仕事量を扶養範囲内に収めるよう制限しなければならないことがあります。こうした収入制限が扶養内で働くフリーランスにとって、デメリットに感じる人も少なくありません。もし、順調に収入が増えて軌道に乗ってきた場合は、扶養から外れることも検討すると良いかも知れません。
フリーランスが入れる2種類の扶養と条件
フリーランスであっても扶養条件を満たせば、問題なく扶養に加入できます。扶養には大きく分けて社会保険上の扶養と税法上の扶養の2種類があります。
以下、それぞれに分けて見ていきましょう。
社会保険上の扶養の場合
社会保険上の扶養は、健康保険や年金の負担を免除するための制度です。条件として配偶者(扶養者)が「厚生年金」に加入していることが必須とされています。また、配偶者が個人事業主またはフリーランスの場合は対象外となるため注意が必要です。年収制限として、フリーランスの年収が130万円未満であることが求められます。
税法上の扶養の場合
一方で税法上の扶養は所得控除を受けられる制度で、所得金額が48万円以下であることが条件です。フリーランスの場合は売上から必要経費を差し引いた所得が対象になるのです。所得が48万円を超えると配偶者控除を受けられなくなるため、確定申告の段階できちんと調整する必要があります。両方の扶養で基準が異なるため、同時にクリアするには所得と収入のバランスに注意しなければなりません。
フリーランスが扶養に入るための手続き方法
フリーランスが配偶者の扶養に入るための手続き方法について、見ていきましょう。
書類の提出先
フリーランスが扶養に入るためには、まず配偶者の勤務先の人事担当部署、または健康組合を経由して年金事務所に提出します。
必要書類
事前準備として、被扶養者は「健康保険被保険者(異動)届」に必要な事項を記入します。その後、申請に必要な添付書類の準備もしなければなりません。詳細は以下をご参考ください。
- 【提出書類内容】
- 健康保険被保険者(異動)届
- 収入を証明する書類(次のいずれか)
- 確定申告書のコピー
- 所得証明書
- 給与証明書
- 離職票のコピー
- 続柄を証明する書類(次のいずれか)
- 戸籍謄本(あるいは戸籍抄本)
- 世帯全員が記載された住民票
申請時のポイントとよくある落とし穴
収入見込みを少なく見積もって申請してしまうと、扶養認定後に収入額が基準を超えた場合、過去に遡って保険料を徴収される可能性があります。申請の際は現実的な収入見通しを提示しておくことが重要ポイントです。また収入増加が予想される場合は、必ず、早めに配偶者の勤務先へ連絡するようにしましょう。
扶養内で働きながらフリーランス活動を続けるコツ
フリーランス活動を続けていく上で、扶養範囲内に収めるためのコツやポイントはどのようなことでしょうか? 以下、2つを見ていきましょう。
年間収入の管理をする
扶養条件を維持するには、年間収入を常に意識することが不可欠です。特に、年末に駆け込み受注をしがちなフリーランスは注意が必要です。ノートやExcelの表などを利用し、収入の記録をつけておくと収入の集計にも大変便利です。さらに、経費の管理もしやすくなり、収入と経費の差を定期的に見直せます。また、月次で収入管理を行うことで、繁忙期でも計画的にセーブできるでしょう。
必要に応じた契約・案件選びをする
高単価案件や長期契約案件を受けた場合、収入額をオーバーしてしまう恐れがあります。扶養内を意識するのであれば、単発案件中心に受注し、収入調整をしやすくしておくことがコツです。どのように案件を受注したいか、具体的に目標を決めておきましょう。案件のリサーチで内容や報酬、納期をきちんと確認して、自分の希望条件をリストにあげておくと無理のない契約・案件選びができるでしょう。
フリーランスが扶養から外れる際のポイント
万が一、収入が扶養基準を超えて、扶養から外れてしまった場合、どのようにしたらよいでしょうか? いざという時のために困らないように、事前に手続きや保険料負担をシミュレーションしておくと良いでしょう。扶養から外されてしまった際のポイントは以下の通りです。
配偶者から扶養元に申告する
まず、配偶者が勤めている会社へ扶養を外したい旨を申告することから始めます。担当から必要な手続きなどを説明してもらえるので、指示に従って速やかに手続きをしましょう。健康保険と年金をセットで手続きをしますが、加入先によって手続きも異なりますので、受け取った書類をよく確認して手続きを進めることがポイントです。
国民健康保険・国民年金への切り替えを行う
一般的には扶養基準を超えて扶養を外されてしまった場合は、国民健康保険および国民年金への切り替えを考えるのが賢明です。国民健康保険料は収入額が多ければ多いほど保険料は高くなりますが、収入額が少ない場合は軽減措置があります。ただし、国民健康保険料の軽減や国民年金の免除は、基本的に世帯全体の所得が少ないことが条件です。もし、本人のみの収入が少なくても、世帯内に高所得者がいる場合は適用されないことがあります。また国民年金の保険料については定額ですが、収入が少ない場合は特例措置(免除申請)についてお住まいの市区町村の役場へ相談してみると良いでしょう。
所得や税金の管理(確定申告の準備)をする
フリーランスは時給で働く従業員とは違って、収入のコントロールが難しいのが特徴です。そのため、自分自身で1年間にどのくらい稼いだかを、確定申告する必要があります。確定申告することによって、どのくらいの税金を支払うのか決定します。
まとめ
フリーランスが扶養内で働くための条件や手続き方法についてご理解いただけたでしょうか? 扶養内で働くメリットとして健康保険料や年金保険料の負担が軽減しますが、年収制限がかかるデメリットもあります。また年収と安定性のバランスが重要ポイントとなるため、社会保険上と税法上それぞれの条件に注意しなければなりません。フリーランスが扶養内で働くために年間収入を管理することを意識しながら、バランスよくコントロールしていきましょう。