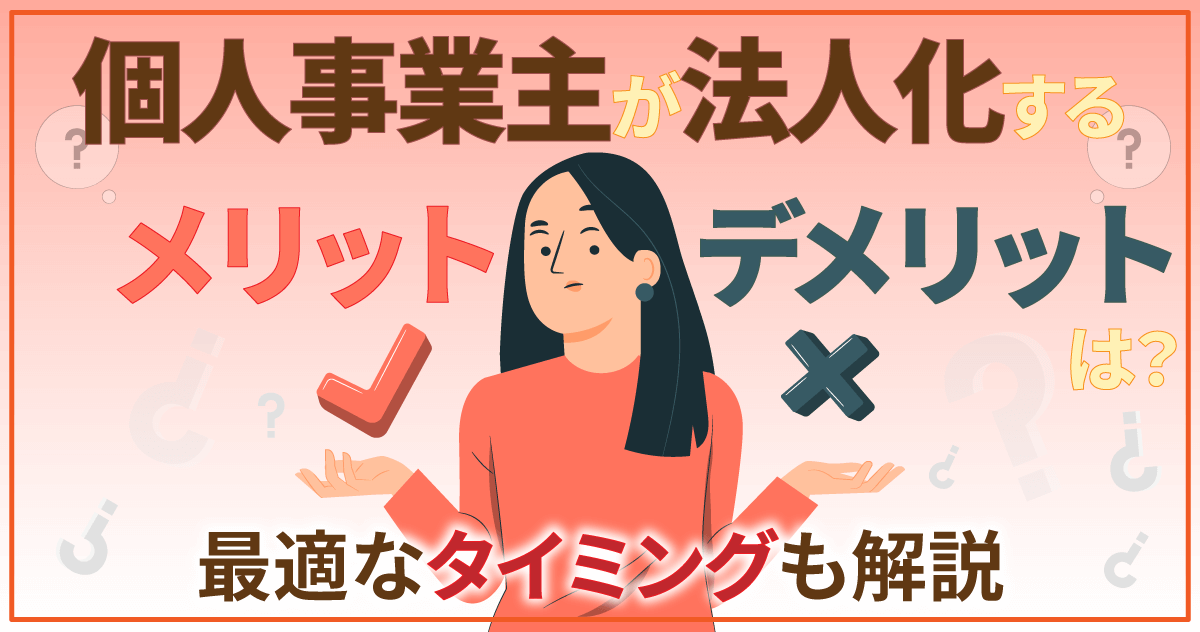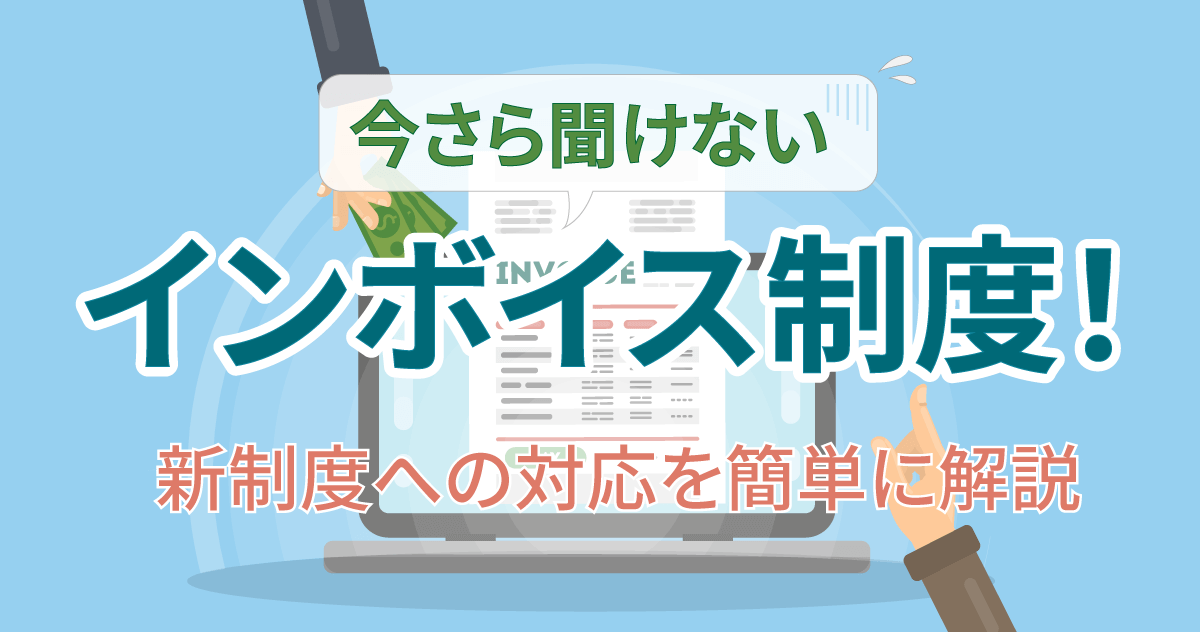インボイス制度とは?仕組み・対応方法をわかりやすく解説

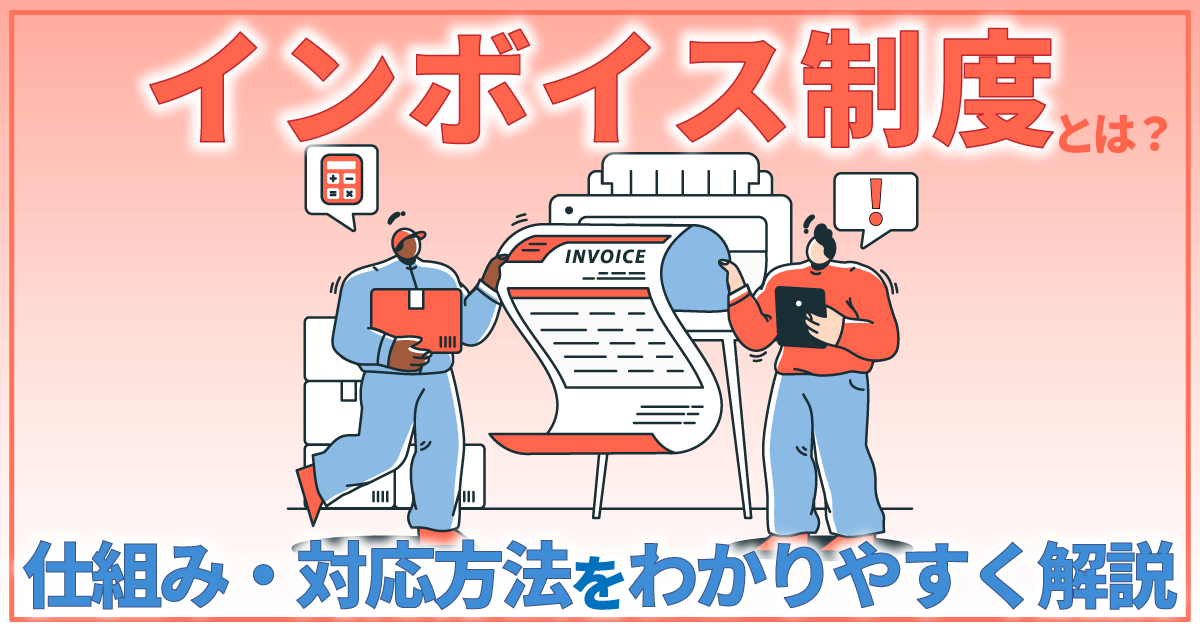
はじめに
- 課税事業者へ登録するかは慎重に検討する
- 免税事業者のままだと取引先が仕入れ税額控除を受けられない
- 課税事業者になるとビジネス上の信頼性の維持に役立つが、消費税の納税義務の発生や経理業務が複雑になる
- 課税事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する
- 会計ソフトや記帳方法などがインボイス制度に対応しているのか確認する
インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月に導入が開始されました。インボイス制度は、適格請求書等保存方式とも呼ばれ、事業者が仕入税額控除を適用するためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。課税事業者のみが控除を受けることができ、発行した請求書には登録番号や税率ごとの消費税額が記載されています。以下では、インボイス制度について詳しく解説していますので、順に見ていきましょう。
インボイス制度の目的
消費税の公平な徴収と適正な申告を実現することが、インボイス制度の目的です。インボイス制度の導入前の従来の制度では、仕入れ先が免税事業者でも、買い手側が仕入税額控除を受けられる仕組みとなっており、税の不透明さや公平性に課題がありました。
そのためこの制度を導入することで、課税事業者のみが発行可能な「インボイス(適格請求書)」を取引の証明としています。
インボイス制度の対象は課税事業者
課税事業者とは、売り上げに対して消費税を上乗せして受け取り、その消費税を国に納める義務がある事業者のことです。年間売り上げが1,000万円を超える事業者や、自ら課税事業者として登録する事業者も対象になります。
個人事業主が受けるインボイス制度の影響
仕入控除を受けるために、取引先がインボイスの発行を求めるケースが増えています。しかし、免税事業者のままだとインボイスを発行することができません。このため、影響を正しく理解し今後の対応を検討することが重要です。
免税事業者のままだとどうなる?
免税事業者は消費税の納税義務がないため、インボイスを発行できません。インボイスがなければ、取引先は仕入税額控除を受けられず、支払った消費税を自社で負担することになります。
その結果、取引先にとって負担となり、取引を見直され終了されるリスクにつながります。こうした影響を避けるため、今後も安定して取引を続けたい事業者は、課税事業者に登録してインボイスを発行できる体制を整えるかどうか、事業の将来を見据えて検討することが重要です。
課税事業者になるとどう変わる?
課税事業者になると、インボイスが発行可能になります。そのため取引先も仕入税額控除を受けられるようになり、双方とも安定した取引を続けられるようになります。
一方で、課税事業者になると以下のような負担も発生します。
- 売上にかかる消費税の納税が必要になる
- 消費税申告書の作成が必要になる
- 帳簿や請求書の管理など、経理作業が増える
これらの負担をあらかじめ理解し、準備できるかどうかも重要な判断材料となります。
登録する?しない?判断のポイント
課税事業者へ登録するか、しないかの判断のポイントは、以下の通りです。
- 取引先が課税事業者で、インボイス発行を必要としてくるのか
- 自分の商品やサービスが法人向けか一般消費者向けなのか
- 経費が多く、仕入税額控除の恩恵を受けたいのか
- 売上や収益に対して消費税納税が大きな負担にならないか
自身の商品の売り方や、取引相手、全体の収支のバランス、経理の体制の4点を総合的に判断し、課税事業者になるのか判断しましょう。
課税事業者になるには?登録の流れと注意点
課税事業者になるには、登録申請が必要です。登録には期限や条件があるため事前によく確認しておくことが重要です。ここでは、e-Tax・書面それぞれの流れと注意点を詳しく解説していきます。
登録申請の方法(e-Tax/書面)
- 利用者識別番号を取得する
- 適格請求書発行事業者の登録申請書をe-Tax上で作成し、送信する
- 登録通知をe-Tax内で確認する
- 税務署や国税庁のHPで申請書を入手する
- 欄に必要事項を記入する
- 税務署に持参または郵送で提出する
消費税の納税義務が発生する
課税事業者になると、売り上げに含まれる消費税を支払う必要があります。消費税は「年1回」を確定申告時に納めることになります。前々年の納付額が48万円を超える場合は、中間納付が年1~4回発生し、確定申告時の納付と合わせて年間計4回の納付が必要となります。
売り上げが増えてきたら納税回数が増える可能性があることも念頭に置いておきましょう。
インボイス対応で見直すべき3つのポイント
インボイス制度の導入に伴って、事業者はこれまでの経理・取引方法を見直す必要があります。重要な以下の3つのポイントを整えることで、スムーズにインボイス制度にも対応できるでしょう。見直すべきポイントについて詳しく解説します。
請求書フォーマットの更新
適格請求書には、登録番号、税率ごとの税抜価格、消費税額などの記載が必須です。
旧来の様式では不十分なため、請求書のフォーマットを見直す必要があります。
会計ソフトの見直し
インボイス発行・受領に対応した会計ソフトの導入が望まれます。登録番号の管理、消費税区分の自動計算、申告書の自動作成ができるかを確認しましょう。
取引先との調整を行う
免税事業者であることを理由に、取引先からインボイスの発行を求められるケースが増えています。
事業の方針を明確にして、取引先に説明できるようあらかじめ準備しておきましょう。
経過措置を活用する方法
インボイス制度には経過措置が設けられており、段階的に縮小されるため、計画的な対応が重要です。以下では、そのポイントを紹介します。
経過措置とは
経過措置とは、免税事業者等からの仕入れでも、買い手が仕入れ税額控除を一部できるようにする特例です。経過措置を適用できる期間は以下のとおりです。
| 制度開始~2026年9月 | 80%の控除が可能 |
|---|---|
| 2026年10月~2029年9月 | 50%の控除が可能 |
| 制度開始~2026年9月 | 控除不可 |
経過措置中にやるべき準備とは
経過措置を有効に活用するために、取引先がインボイス対応可能なのか、課税事業者になるかどうかの収支シミュレーションも行いましょう。そして、税務申告の準備や請求書フォーマットの更新、会計ソフトをインボイス対応なソフトにしておきましょう。これらをこの経過措置中に整えておくことで、完全移行後も安心です。
登録しない戦略はアリ?
一般消費者向け(美容師や小売り、教室業など)は、顧客が仕入れ税額控除を行うことがないため、インボイスの有無が取引に影響しないケースが多くあります。そのため、インボイス発行事業者として登録しないという選択肢もあるでしょう。
一方、法人向け(ITやコンサル業など)は、インボイス発行ができないと取引が減るというリスクがあるため、登録を検討する価値があります。
インボイス制度に向けたチェックリスト
インボイスへ登録しようか迷っている個人事業主の方のために、判断材料となるチェックリストを用意しました。チェックリストをもとに、自身の方向性を決めてみましょう。
登録の必要性チェック項目
以下のチェックリストに対して、当てはまっている数が多ければインボイスへの登録を積極的に検討してみてください。
- 取引先が法人や課税事業者が多い
- 取引先にインボイス発行を求められている
- 商品・サービスに消費税を含めて請求している
- 今後も取引を拡大していきたい
- 取引先との良好な関係を維持し、安定した取引をしていきたい
まとめ
インボイス制度への対応は、今後の取引先との関係や事業継続に関わってくる重要なポイントです。課税事業者へ登録する場合は、今後の事業の方向性に合わせてチェックリストを参考にして慎重に判断をしていきましょう。そして、請求書フォーマットの更新や会計ソフトの準備など、経過措置を有効活用しながら、少しずつ完全移行までに整えておくことをおすすめします。