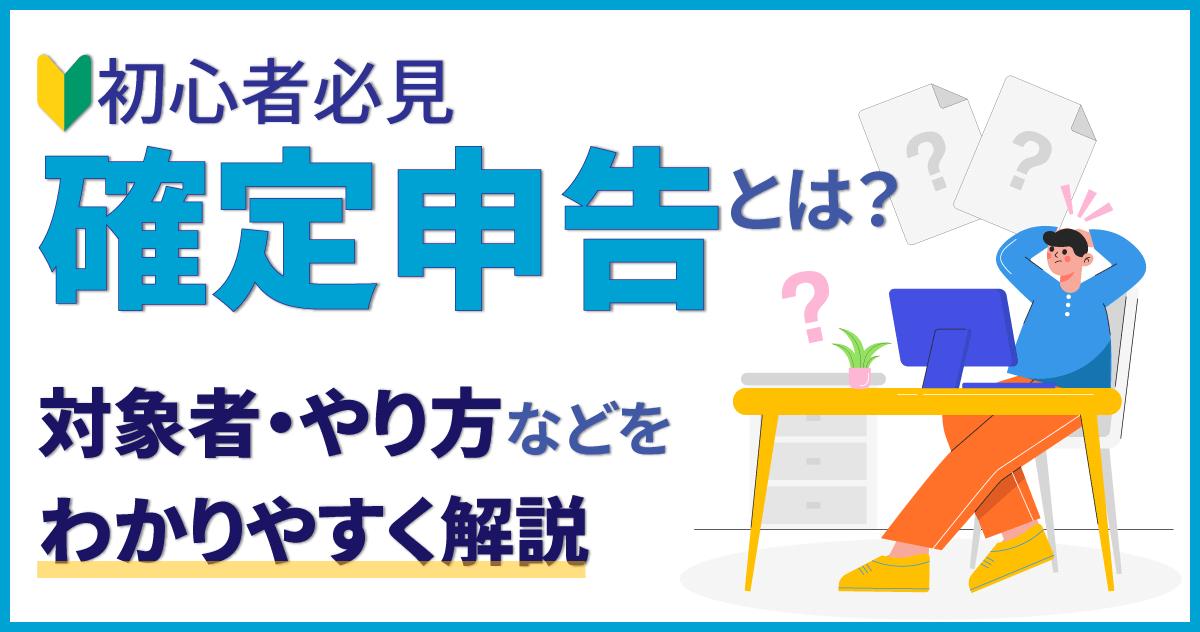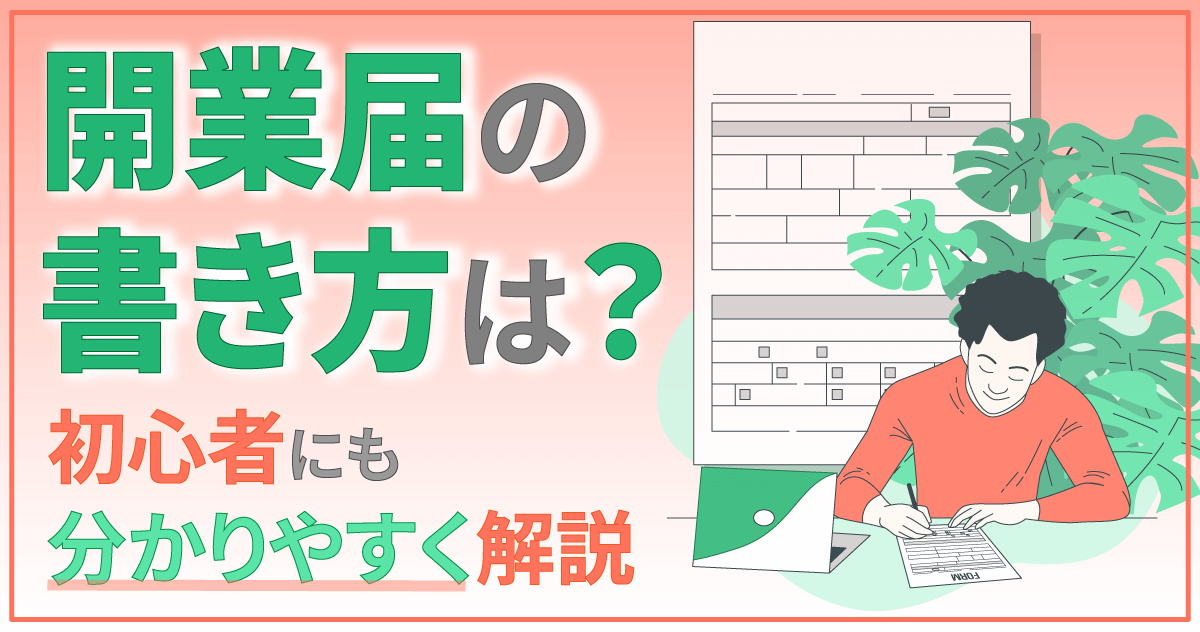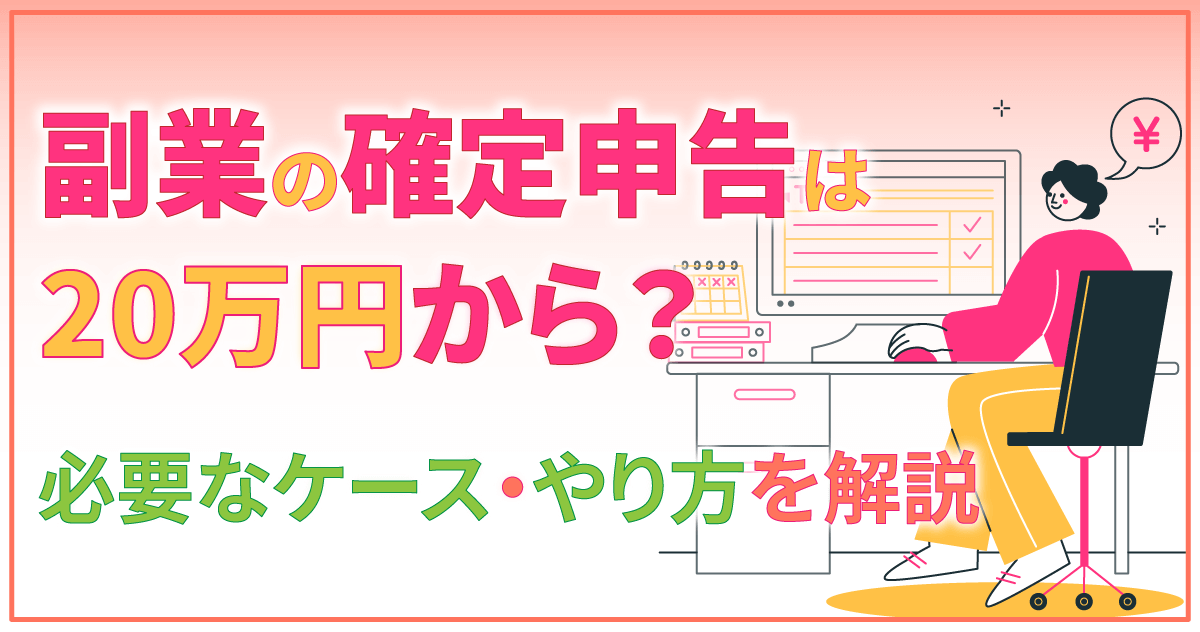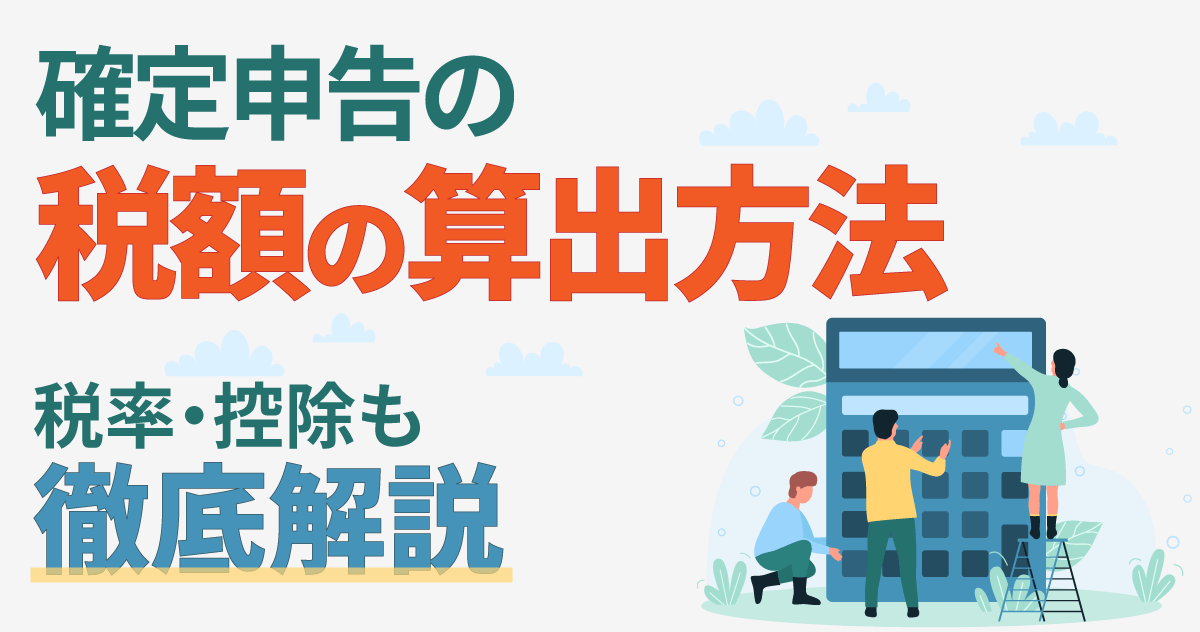青色申告とは?フリーランス・個人事業主向けに制度とメリットを解説

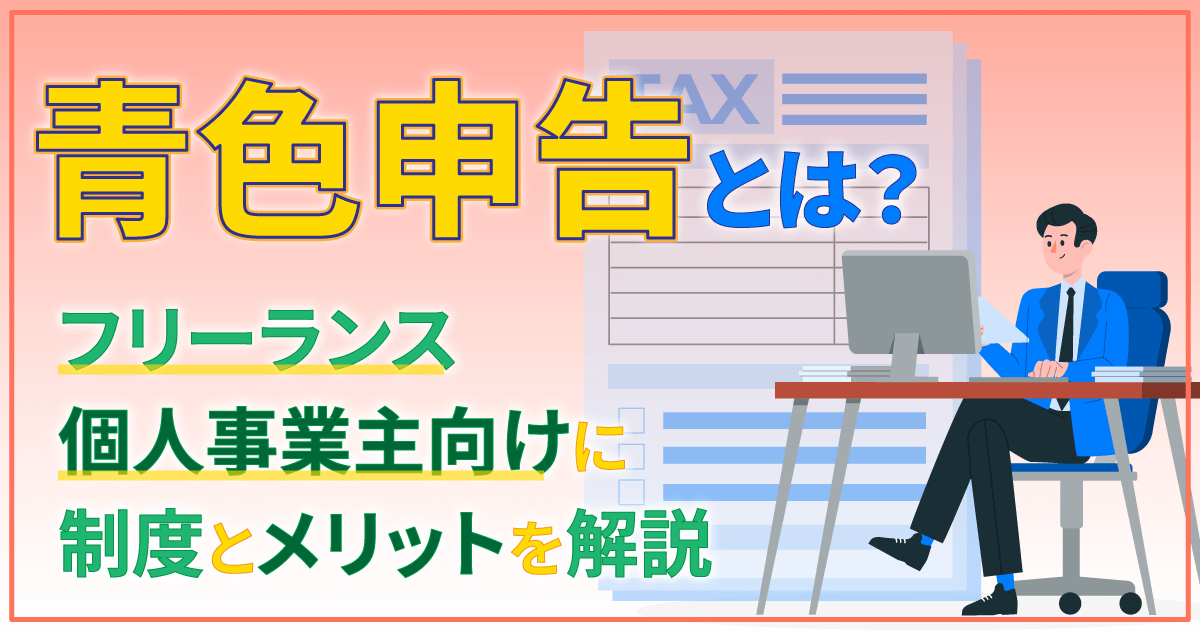
はじめに
- 青色申告は確定申告の一種である
- 青色申告には最大65万円の控除などの特典ある
- 青色申告をおこなうには事前申請と複式記帳が必要である
- 記帳が難しい場合は会計ソフトを利用するか税理士に依頼する方法がある
- 青色申告の疑問点は放置せず税務署窓口などに相談しよう
青色申告とは
青色申告とは、確定申告の方法のひとつです。確定申告は、1年の所得金額を確定し、そこから所得税を算出する手続きです。青色申告は個人事業主やフリーランス、法人が選択できる確定申告の方法であり、最大65万円の控除などの特典をうけることができます。
ただし、青色申告をするための事前申請が必要だったり、複式記帳をおこなう必要があったりと、手間も発生します。
この記事では青色申告のやり方やメリット・デメリットについてくわしく解説します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれの違いは以下の通りです。
- 白色申告
白色申告は、帳簿の付け方が簡単だがあまり節税効果がない確定申告の方法だ。青色申告をしない場合、白色申告で確定申告をすることになる。
- 青色申告
個人事業主や法人が選択できる確定申告の方法が青色申告だ。ただし、青色申告をする場合は事前の申請が必要である。青色申告をするためには、1年の収支記帳と決算を複式記帳という複雑な方法でおこなわなければいけないが、最大65万円の控除を受けられたり、その他にも特典があったり、節税効果が大きい確定申告の方法である。
青色申告は、前述の通り帳簿のつけ方が複雑になって白色申告よりも難易度があがります。帳簿ソフトを利用して記帳したり 、仕事に関わるレシートや領収書をすべて保管したりする必要がでてきます。収支が大きかったり複雑すぎたりするような場合は、税理士への依頼が必要になることもあり得るでしょう。しかし手間がかかる分、大きな節税効果があります。
青色申告できる条件
青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある個人が対象です。たとえば、個人事業主・フリーランスで事業所得がある人や、所有している不動産によって所得がある人です。給与所得や雑所得のみでは青色申告対象者とならない(白色申告となる)ので注意しましょう。
青色申告が向いている人
青色申告に向いている人は以下の通りです。
- フリーランス・個人事業主で白色申告をしている人
- これから事業を始めようとしている人
- 事業が赤字になりそうな人
それぞれ解説します。
フリーランス・個人事業主で白色申告をしている人
フリーランス・個人事業主で今まで白色申告をしていた人は、青色申告にした方が大きく節税できるでしょう。
なお、これまで白色申告において記帳は必要なかったのですが、2014年1月より、白色申告でも簡易記帳の義務が生じました。したがって現状は、白色申告でも青色申告でも確定申告の手間は以前より減っている状況です。このため、似たような手間がかかるのであれば、青色申告をした方が節税できるのでオススメといえます。
これから事業を始めようとしている人
青色申告で確定申告をおこなうためには、税務署に事前の届け出が必要になります。このため、税務署で開業届の提出をするとき、同時に青色申告の申請も済ませてしまうと大変便利です。
事業が赤字になりそうな人
青色申告で確定申告をすると、決算時の赤字を3年間繰り越せるため、白色申告よりも節税効果があがります。とくに事業の開始直後は赤字になることが予想されるため、開業と同時に青色申告をはじめるのはやはりオススメといえます。
サラリーマンで副業している場合は?
サラリーマンで副業をしている場合、確定申告は、副業分を雑所得として白色申告で申請するパターンがほとんどです。しかしながら、事業規模や事業金額によっては青色申告ができることもあるため、青色申告が可能かどうか迷ったときは、税務署で相談するとよいでしょう。
青色申告のメリット
青色申告で確定申告をおこなう主なメリットは、以下の5つです。
- 青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
- 家族の給与(青色事業専従者給与)を経費扱いできる
- 赤字を3年間繰越ができる
- 減価償却の特例を受けられる
- 貸倒引当金を計上できる
それぞれ詳しく解説します。
青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
青色申告では、一定の要件を満たしたときに、65万円、55万円、10万円の特別控除を受けることができます。
まず、最大の控除額である65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 不動産所得または事業所得があること
- 複式簿記で帳簿をつけていること
- 帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する
- e-Taxで青色申告をおこなうか、もしくは2の帳簿を電子保管する
55万円の控除は、この要件のうち1~3までを満たすと受けられます。
65万円・55万円の要件を満たさなかったとき、または確定申告の期限までに提出が間に合わなかったときは、10万円の控除になります。
まとめると、次の通りです。
| 青色申告特別控除を受けるための要件 | |
|---|---|
| 65万円控除 | 次の条件をすべて満たすことが必要である ・不動産所得または事業所得があること ・複式簿記で帳簿をつけていること ・帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する ・e-taxで青色申告をおこなうか、もしくは帳簿を電子保管する |
| 55万円控除 | 次の条件をすべて満たすことが必要である ・不動産所得または事業所得があること ・複式簿記で帳簿をつけていること ・帳簿をもとにした貸借対照表を確定申告書に添付する |
| 10万円控除 | 65万円・55万円の要件をみたしていないときや、確定申告の提出期限日に間に合わなかった場合、最大10万円の控除となる。 |
なお、実際の所得税の計算方法はルートテックでも詳細に解説しています。
家族の給与(青色事業専従者給与)を経費扱いできる
青色申告では、配偶者や家族に支払った給料を経費扱いにすることが可能です。ただし経費扱いにするためには、事前に管轄の税務署に青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。なお、事前に届けた給与額より大きい額の給与は経費とすることができないので注意しましょう。
参考:国税庁|No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、3年間にわたって赤字の繰り越しができます。つまり、決算で赤字が出た翌年以降に黒字が出た場合、そこで赤字の清算ができるということです。
減価償却の特例を受けられる
減価償却とは、固定資産の購入費用を使用期間にわたり分割して費用として計上する処理のことです。
青色申告では、通常分割して計上する減価償却を取得価格が30万円未満であれば一括して計上することが可能です。分割計上しなくてよくなるため、節税できる範囲が広がります。
貸倒引当金を計上できる
青色申告では、貸倒引当金を計上できます。貸倒引当金とは、取引先の倒産などで売掛金が回収不可となるリスクを見越して、あらかじめ計上しておく勘定科目のことです。
つまり、貸倒引当金を計上することで、将来の貸し倒れリスクに備えつつ、所得の圧縮が可能です。
なお、金額の設定には上限があり、年末時点における売掛金などの債権残高の5.5%以下(金融業では3.3%以下)を貸倒引当金繰越として計上できます。
青色申告のデメリット
確定申告を青色申告でおこなうデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
- 事前申請が必要
- 複式簿記で帳簿をつける必要がある
- 65万円の控除を受けるにあたりe-Taxによる電子申請が必須
それぞれ解説します。
事前申請が必要
確定申告で青色申告をおこなうためには、事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、白色申告をおこなうための申請はとくにないため、比較してデメリットといえるでしょう。
なお、青色申告をしたくても、青色申告承認申請書の提出をしていなければ、白色申告しかできません。
複式記帳をおこなう必要がある
青色申告をおこない65万円・55万円の控除をうけるためには、1年の収支について、複式記帳をおこなわなければなりません。複式記帳は二重で記帳する複雑な記帳方法であるため、かなり手間がかかります。これは青色申告でよくいわれるデメリットです。
対策としては、会計ソフトを利用して確定申告する、税理士に依頼するといった方法があります。
65万円の控除を受けるにあたりe-Taxによる電子申請が必須
青色申告で65万円の控除を受けるには、e-Taxによる電子申請か、または、複式記帳の帳簿を電子保管する必要があります。デジタルが苦手な人やPCを所有していない人には、大きなデメリットといえるでしょう。
青色申告の方法と期限
確定申告での青色申告は、以下の順番でおこないます。
- 事前に税務署に申請をする
- 申告に必要な書類を準備する
- 確定申告書を作る
- 確定申告をおこなう
なお、確定申告できる期間は決まっており、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。ただし、初日や最終日が土日祝日の場合は、翌平日になります。青色申告の提出が最終日に間に合わない場合、ペナルティとして控除額が減る可能性があります。期間中に余裕をもって提出できるようにしましょう。
1.事前に税務署に申請をする
前項で解説した通り、青色申告をおこなうためには、事前に青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出する必要があります。申請期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(ただしその年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをしたりした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)です。提出を忘れた場合、その年は白色申告しかできません。
2.申告に必要な書類を準備する
申請を終えて、確定申告の期日が近づいてきたら、青色申告に必要な書類を準備します。必要な書類は以下の通りです。
- 青色申告決算書
- 確定申告書
- 添付資料
帳簿による決算書を作成し、付随する資料があれば添付します。これらをもとに、確定申告のための所定の用紙である「確定申告書」を記入することになります。
青色申告決算書
1年間の事業収支を表す重要な書類です。複式記帳による決算書を作成するには簿記の知識が必要ですが、近年では有料の会計ソフトに収支を入力するだけで自動的に複式記帳をしてくれるサービスが登場しています。個人事業主の方は、有料でもこちらを利用すると容易に青色申告できるのでオススメです。
添付資料
青色申告決算書の収支を証明する資料を添付します。
例:レシートや領収書、生命保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの控除証明書・掛金払込証明書、ふるさと納税の受領証明書など
確定申告書
確定申告には専用の用紙があります。以前は白色申告と青色申告は別の用紙でしたが、今は同一の様式に統一されています。電子申請(e-Tax)の場合は紙の申告書は必要ありませんが、記入したものを郵送する場合は、紙の申告書で提出することになります。事前に税務署などで確定申告用の申告書用紙を入手するか、国税庁のサイトからテンプレートをダウンロードして印刷しておきましょう。
参考:国税庁|所得税の確定申告
3.確定申告書を作る
決算書をもとに、確定申告書の作成をします。確定申告書の作成方法は複数あります。
- e-Tax(確定申告書作成コーナー)
- 会計ソフトによる出力または申告
- 手書き
e-Taxは、確定申告書作成コーナーというインターネットのWebページにアクセスして、オンラインで確定申告する方法です。
会計ソフトや確定申告ソフトは、複式記帳を自動でおこなってくれますし、e-Taxと連携してオンラインで確定申告がおこなえるものも多いので大変便利です。
手書きの場合は、確定申告用の用紙を使って記入します。
4.確定申告をおこなう
確定申告書が完成したら、確定申告をおこないましょう。申請方法は複数あります。
- 電子申請(e-Tax)
- 税務署の確定申告書作成コーナーで作成する
- 手書きの確定申告書を持参して税務署に提出する
- 手書きの確定申告書を税務署に郵送する
なお、郵送の場合は、消印の日付が提出日となります。
青色申告の際の注意点
確定申告を青色申告でおこなう際に注意すべきポイントを解説します。
保管が数年必要な書類がある
確定申告の際につけた帳簿やレシートなどの書類は、数年間の保管義務があります。白色申告と青色申告でそれぞれ保管期間が決められています。
青色申告の場合は次の通りです。
- 帳簿
保管期間:7年
- 決済関係書類
貸借対照表、損益計算書といった決算関係書類のこと。保管期間:7年
- その他関係書類
現金などのやり取りが記載されたレシート・領収書や生命保険の控除証明書など、通帳のコピーなどといった関連書類のこと。保管期間は原則7年だが、前々年分の事業所得・不動産所得が300万円以下のときは5年。
遅延や不正はペナルティがある
確定申告の遅延や不正は、追徴課税や青色申告承認の取り消しといったペナルティを受けることがあり得ます。
主な例は以下の通りです。
- 確定申告をしなかった場合、無申告加算税が課され、通常より納税金額が増える
- 期限後に確定申告をした場合は延滞税が課される
- 故意に所得を隠した場合、重加算税が課される場合がある
- 脱税や隠ぺいなどの行為をおこなった場合、青色申告の承認取り消し、さらには刑事罰(罰金・懲役)を受けることがある
- 2事業年度連続で期限内に申告が行われなかった場合、青色申告の承認が取り消しになることがある
参考:国税庁|法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
疑問点がある場合は相談を
疑問点がある場合はそのままにせず、税務署や税理士による無料相談などの相談可能な窓口に相談しましょう。確定申告の内容が不正確な場合には追徴課税がかかることもあり、本来の金額より大きな金額が後から課される可能性もあるからです。
なお、相談窓口は複数あり、特に確定申告期間中は出張相談などが増えます。疑問点がある場合は積極的に利用を検討するとよいでしょう。
相談できる主な窓口や、参考になるWebサイトは以下の通りです。
- 所轄の税務署窓口(対面または電話)
- 青色申告会(相談するには有料会員になる必要があるので注意)
- 利用中の会計ソフトサポートサービス
- 税理士による無料相談会(確定申告期間中に商工会議所などでおこなわれる)
- インターネットのQ&Aサイト
まとめ
個人事業主やフリーランスは毎年確定申告をおこない、所得税を確定させる必要があります。確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、個人事業主やフリーランスは青色申告が可能です。
青色申告では、最大65万円の控除を受けられるほか、家族の給与を経費として計上できる、赤字の清算や減価償却の特例が利用できるなど、数多くのメリットがあります。ただし、青色申告にはデメリットもあり、手間がかかる複式記帳をおこなう必要があったり、青色申告をするための事前申請をしなければいけなかったりというデメリットもあります。
記帳が手間である場合は会計ソフトを利用する方法がオススメです。事業規模が大きかったり会計処理が複雑だったりという場合は、有料で税理士に依頼する方法もあります。
また、青色申告で不正や遅延をした場合はペナルティが課されます。そのため、疑問点は放置せず税務署窓口や税理士による無料相談会で相談したり、インターネットのQ&Aサイトを参考したりして正しく申告をおこなうようにしましょう。